目次
シンセサイザーを始めたいと思ったあなたへ

「バンドでキーボードを担当することになった!」
「曲作りやDTMに挑戦してみたい!」
「家でも気軽に音楽を楽しめる楽器がほしい!」
そんな気持ちが芽生えたらシンセを始めるタイミング⭐️
シンセはバンドからDTMまで幅広く活躍する楽器です!
でも実際に選ぼうとすると「アナログ?デジタル?」
「音源方式って?」「鍵盤の数は?」などなど
知らない言葉が多くて、どれを選べばいいか迷ってしまいますよね。🤔
そこで今回は、初心者の方にもわかりやすく、選び方のポイントやおすすめモデルをご紹介します!
気になる1台を見つけるヒントに、ぜひチェックしてみてください。
シンセサイザーの基本構造と種類
■ シンセサイザーってどんなしくみ?
バンドで使用されるシンセサイザーは、ピアノやストリングス、ブラス、シンセリードなど、
さまざまな音を一台で鳴らせる多機能な鍵盤楽器です。
メロディやコード、パッドのような音を演奏するなど、曲中での役割は実に多彩。
ここでは、そんなバンド向けシンセに搭載されている主な構成要素を見ていきましょう。
▸ 音源部(TONE GENERATOR)
シンセの音を生み出す核となる部分。
バンド向けモデルでは、アコースティックピアノやエレクトリックピアノ、オルガン、シンセサウンドなど、実用的な音色が豊富に内蔵されています。
▸ 鍵盤部(KEY ACTION)
演奏スタイルや好みによって、鍵盤のタッチにはいくつかの種類があります
・軽くて素早い演奏に向いたシンセ鍵盤
・少し重みがあり安定感のあるセミウェイト鍵盤
・ピアノに近い弾き心地のピアノタッチ鍵盤
▸ コントロール部(操作パネル)
音色切り替えやエフェクト操作などをリアルタイムで行う部分。
ライブでは、直感的に扱えるかが重要なポイントです。
▸ エフェクト・EQ
音に厚みや空間を加えるための処理。
リバーブやコーラス、EQなどで、バンド全体になじむ音作りができます。
▸ 接続端子・電源まわり
LINE OUT、USB、MIDIなどの入出力端子に加え、スピーカーや電池駆動の有無も確認を。
演奏スタイルや使用環境に合った構成かどうかを見ておきましょう。
初心者におすすめの選び方ポイント

シンセサイザーを選ぶときは、使い方に合った機能が備わっているかどうかがとても大切です。
演奏に必要な音色が入っているか、操作は直感的か、持ち運びやすいかなど、
目的に合ったモデルを選ぶことで、練習や制作がぐっと快適になります。
この記事では、これからシンセを始める方に向けて、自分に合った一台を選ぶためのポイントをご紹介します。
■ ① サイズと重さは「持ち運びやすさ」で選ぶ
バンドで使う場合は、スタジオやライブへの持ち運びやすさも大切なポイントです。
軽くてコンパクトなモデルなら、移動やセッティングもスムーズにこなせます。
一方で、88鍵のピアノタッチ鍵盤や大きめの操作画面が欲しい場合は、
多少重さがあるモデルになることもあるため、使用シーンに合わせて無理のないサイズ感を選ぶのがポイントです。🌟
■ ② 音色の種類は「使いたい音」が入っているかをチェック
ピアノやエレピ、ストリングス、ブラス、シンセリードなど、
バンドでよく使う音色がしっかり収録されているかは大きなチェックポイントです。
また、新しいモデルほど音の再現度やリアルさが高くなっている傾向があるので、
同じジャンルの音色でも、年代や機種によって印象が大きく変わることもあります。
メーカーごとの音作りの個性にも注目しながら、自分の好みに合った音を探してみましょう。🌟
■ ③ 操作性は「すぐに使えるか」で選ぶ
ライブやリハーサルでは、音色の切り替えや調整をスムーズに行えることがとても重要です。
音の切り替えや、複数の音を重ねるレイヤー/分けるスプリット、エフェクトの調整など、
ステージ上で迷わず使える直感的な操作性は大きなポイントです。
さらに、よく使う音色を簡単に登録・呼び出しできる“バンク機能”の使いやすさもチェックしておきたいところ。
セットリストに合わせて音色を並べたり切り替えたりする際、バンク操作がわかりやすい機種ほど実戦向きです。
ボタン配置や画面の見やすさも含めて、「これなら分かりやすい!」と感じるモデルを選ぶのがおすすめです。🌟
■ ④ あるとうれしい“プラス機能”もチェック
シンセサイザーには、演奏や制作の幅を広げてくれる便利な機能が搭載されているモデルもあります。
たとえば、
・スピーカー内蔵タイプならアンプなしでもすぐに音が出せて手軽
・サンプラー搭載モデルなら、効果音やフレーズを再生できてライブでも便利
・アルペジエーターやパッド付きモデルなら、アイデア出しや表現の幅が広がります
「これがあると便利そう!」と思える機能があるかどうかも、選ぶ際の参考になります。🌟
■ ⑤「先輩と同じモデル」は、いちばんの近道かも?
はじめてのシンセは、操作や設定でつまずくことも少なくありません。
そんなとき、学校やバンドの先輩と同じ機種を使っていれば、すぐに教えてもらえたり、セッティングの共有がしやすかったりと、とても心強いです。
また、使用者が多いモデルはネットや動画で情報が見つけやすく、独学でも学びやすいのもメリット。
はじめの一台は「周りと同じ」が、実は大正解なこともあります!
「なんとなくいい音だな」「これ、面白そう」
「使いやすそう」——
そんな感覚から選んだ一台が、きっとあなたにとってのベストな選択になります。
店頭ではさまざまなモデルをご用意していますので、ぜひ実際に触れてみてください。
気になる音や操作感を、じっくり確かめてみましょう。
シンセサイザーを始めるときに必要なものまとめ

シンセサイザー本体は、スピーカーを内蔵していないモデルがほとんどです。
多くの場合は本体のみで販売されており、必要な付属品は別途そろえる必要があります。
ここでは、最初にそろえておくと安心な基本アイテムをご紹介します。
■ 揃えておくと安心なものリスト
・ケース(ソフトケース or キャリータイプ)
スタジオやライブへの持ち運びには必須。
サイズに合ったケースがあると、大切な機材をしっかり守れます。
※価格の目安:1万円前後〜
・ダンパーペダル(サステインペダル)
ピアノやエレピなど、音を自然に伸ばしたいときに使用します。
ピアノタッチのモデルを選んだ場合は特に重要です。
※価格の目安:2千円前後〜
・ヘッドホン(イヤホン)
周囲を気にせず練習したいときや、細かい音の確認に便利です。
正確な音をチェックできるモニタータイプが安心です。
・モニタースピーカー (小型アンプ)
スピーカーが内蔵されていないモデルでは、音を鳴らすために外部スピーカーやヘッドホンを使います。
・スタンド(必要に応じて)
安定した演奏姿勢を確保するためにあると便利です。
お客様からよく聞かれること、答えます!
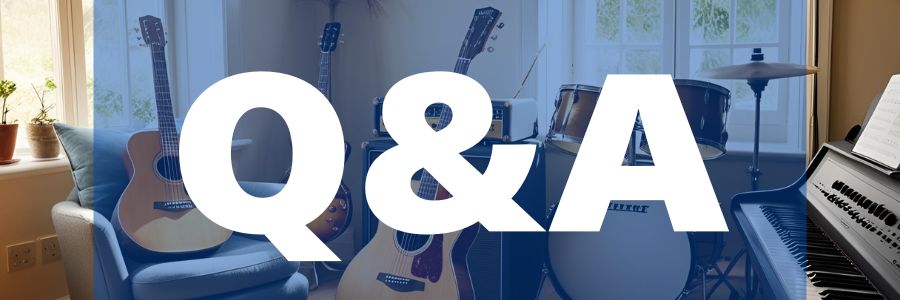
Q. 何鍵盤を買うべきでしょうか?
A. バンドスタイルでよく使われるのは61鍵のモデルです。クラシックのように鍵盤の端まで使うことは少なく、このレンジで十分に演奏できます。
サイズ的にも演奏しやすく、持ち運びにも適しており、作曲からライブまで幅広く対応できるのが特長です。
ピアノ演奏を重視する方には、88鍵のピアノタッチモデルもおすすめですが、そのぶんサイズや重量があるため、使用環境や目的に合わせて選ぶのがポイントです。
Q. 通販とお店での購入、どちらがおすすめですか?
A. ネット通販も便利ですが、鍵盤の弾き心地や操作画面の見やすさ、音色の印象などは実際に触れてみないとわかりにくい部分です。
店頭では、音を出しながら比較できたり、スタッフに相談できるのも大きなメリット。
気になるモデルがある方は、ぜひお店で試してみてください!
Q. スピーカーが付いていないと困りますか?
A. ステージ用のシンセはスピーカー非搭載が一般的です。そのため、外部スピーカーやヘッドホンの接続がないと音が出せません。
本体とあわせて必要な機材をそろえれば、問題なく使えますのでご安心ください。
Q. 買った後にうまく使えるか不安です。
A. 最近の入門機は、操作がシンプルで、使いやすさにも配慮された設計になっています。
当店でご購入いただいた楽器については、音作りや操作方法なども、いつでも気軽にご相談いただけます。
「この曲のあの音ってどんな音色?」「どんなシンセを使ってるんだろう?」といった
楽曲中の音の正体を探りたいときも、スタッフがやさしくサポートいたしますのでご安心ください。
【国内3大ブランドの入門モデル紹介】
シンセ初心者に人気の国内3大ブランド
【YAMAHA・Roland・KORG】
今回はその中から、持ち運びやすくて使いやすい
61鍵モデルを厳選してご紹介します!
■ YAMAHA CK61
CK61の詳細はこちらをクリック👇
2024年、最も売れたシンセサイザーといえばこれ!
今回ピックアップした3台の中でも、音色数は363種類とやや控えめに感じるかもしれません。
ですがこれは、ただ“少ない”わけではありません。
リアルタイム演奏で本当に必要な音色だけを厳選した結果──
無駄を削ぎ落とした、実戦仕様のラインナップにたどり着いたのです。
(正直、1,000音色以上あっても全部は使いきれないよな…と思ってしまうのが本音ですよね。)
CK61は、音色を細かく作り込むよりも“演奏しやすさ”を最優先に設計されたモデル。
この割り切りが逆に新しく、「ステージキーボード」という新たなジャンルを確立しました。
■ スピーカー内蔵&電池駆動に対応!
そして最大の特徴は、スピーカー内蔵!
コンパクトながら音質も良く、ライブ前の控室でのウォームアップや、気軽な音出しにもぴったりです。
さらに電池駆動にも対応しており、ケーブルレスでどこでも練習できるという快適さも魅力。
■ 価格以上の機能性に驚き!
この価格帯でなんと、オルガン用のドローバーやBluetooth入力まで搭載。
思わず「これでできないことって何?」と口にしてしまうほど、充実の一台です。
これは売れるべくして売れた、納得の大ヒットモデルです!
■ Roland JUNO-D6

JUNO-D6の詳細はこちらをクリック👇
初心者からライブキーボーディストまで――
圧倒的な支持を集めるシリーズの最新作!
「この音が欲しい」にしっかり応えてくれるから、ソロでもバンドでも、1台あれば即戦力。
“欲しい音が絶対に見つかる”って、やっぱり正義です。
■ ツマミ・フェーダーで“今”の音が作れる!
JUNOシリーズの大きな魅力が、リアルタイム操作のしやすさ。
ツマミやフェーダーを使ってその場で音を変化させられるから、ライブ中でも自分だけの音を即興で作る楽しさがしっかり味わえます。
これぞまさに、JUNOの真骨頂!
■ 打ち込みにも、配信にも対応!
USBオーディオ機能を搭載しているので、パソコンにつなぐだけでそのまま録音OK!
配信やDTMにもすぐ活用できるため、ライブ派も打ち込み派もどちらにもハマる万能機です。
■ 軽量&電池駆動でどこでも演奏OK!
本体は軽量かつ電池駆動にも対応。
リハーサルスタジオはもちろん、控室やストリートでも電源なしで演奏できる手軽さは大きな魅力。
■ 妥協したくない人にこそ選ばれる一本!
ライブでも音作りでも、どちらも妥協したくない。
そんな“欲張りなキーボーディスト”にこそ使ってほしい、次世代のスタンダードモデルです。
■KORG KROSS2-61-MB

KROSS2-61の詳細はこちらをクリック👇
2024年の今も支持され続ける、ロングセラーモデルの代表格。
KORG KROSS2-61は、ひとことで言えば「全部入りの超優等生」。
エレピやシンセだけでなく、分厚いストリングスやSE系まで、膨大な音色数が収録されており、どんなジャンルにも柔軟に対応します。
さらに、好みの音を重ねたり、加工したり、細かく調整したりといった音作りも思いのまま。
「音を育てたい」人にこそぴったりの、音作りに強い一台です。
■ サンプラー機能で、自由度がさらにアップ
KROSS2の大きな魅力のひとつが、本体にサンプラー機能を内蔵していること。
声や効果音など、自分の音を取り込んで鍵盤で鳴らすことができるため、
アイデアをすぐカタチにできる柔軟さは、クリエイターにもライブ派にも大好評です。
■ USBオーディオ対応・電池駆動・軽量設計
USB接続で録音や配信にもそのまま対応。
さらに電池駆動や軽量ボディのおかげで、どこにでも持ち運べてすぐに使えます。
ステージでも、スタジオでも、自宅でも、しっかり馴染む万能仕様です。
■ 本気で音を作りたいあなたに
「自分だけの音を作りたい」「曲作りにも使い込みたい」
そんな本気派にも応えてくれる、信頼感抜群の頼れる一台です。
【各モデルの特徴比較】
| モデル名 | 特長・ポイント | 向いている使い方 | 重さ | 発売年 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA CK61 | ・マイク入力あり ・ボーカルエフェクト搭載 ・即戦力の音色が多数 | 弾き語り・シンプルなライブ演奏 | 約5.6kg | 2023年 |
| Roland JUNO-D6 | ・直感的な操作パネル ・シンセらしい音が豊富 ・ノブ/パッド付きで音作りも楽しめる | バンド演奏・サウンドメイク | 約5.3kg | 2024年 |
| KORG KROSS2 61 | ・サンプラー/シーケンサー内蔵 ・SDカードでデータ管理可能 ・多機能かつ軽量 | DTM・作曲・多用途 | 約4.3kg | 2017年 |
【各モデルの動画を集めました!】
【まとめ|色々聞いて直感で選ぼう!】
シンセサイザーは、バンドでも自宅でも、自由な音づくりを楽しめる魅力的な楽器です。
最初の1台にぴったりのモデルが見つかれば、演奏も制作ももっと楽しく広がっていきます。
気になるモデルがあれば、ぜひ実際に触って、音を出して、あなたに合った一台を見つけてみてください。
はじめてのシンセ選び、目一杯楽しんで選びましょう!


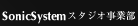



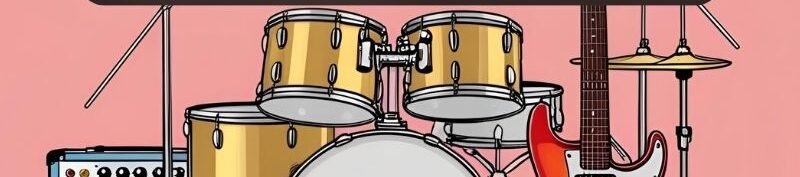

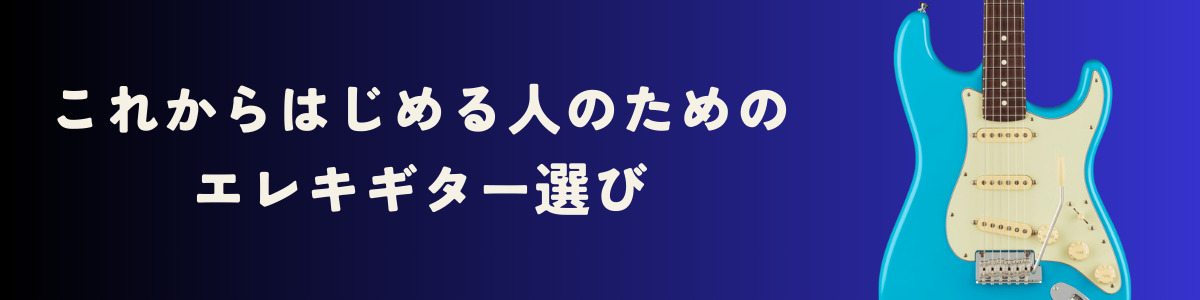
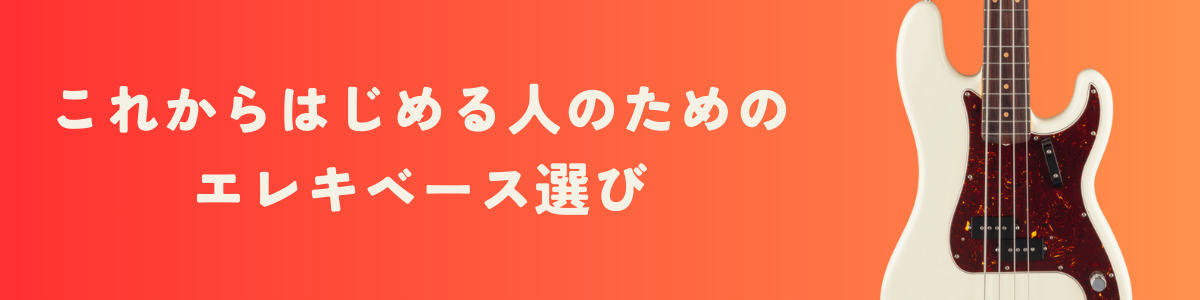
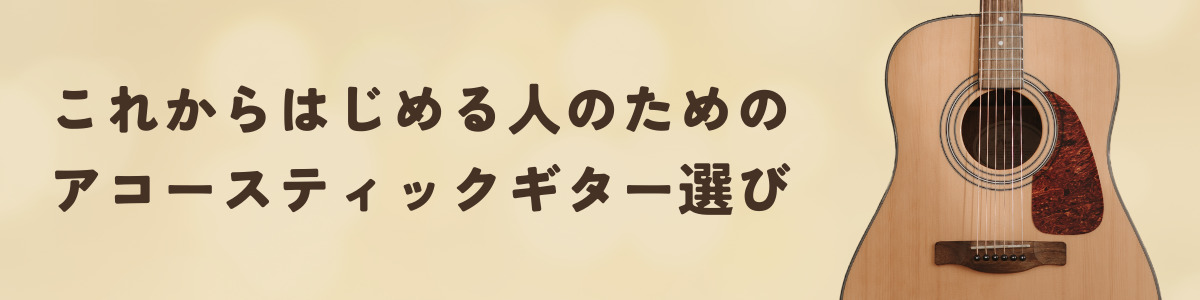
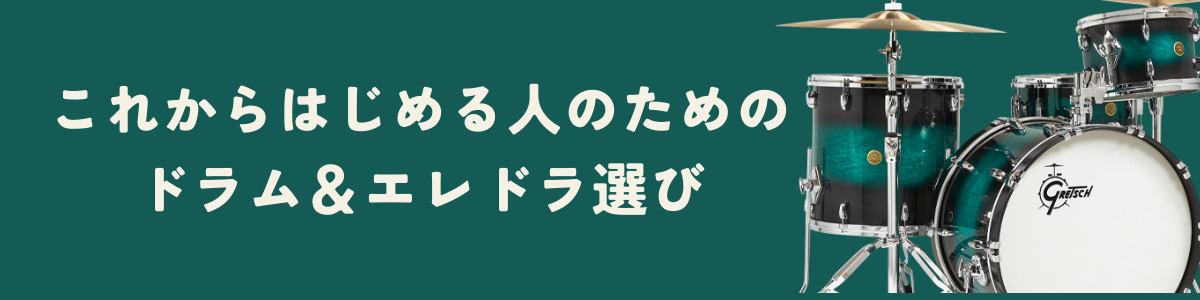
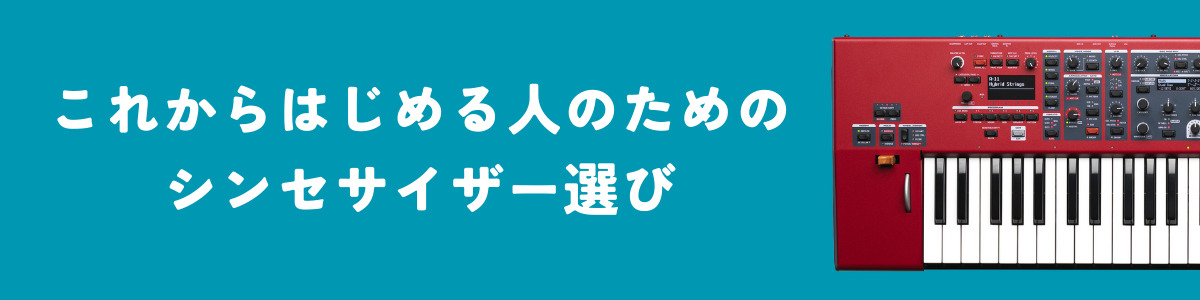
 店舗外観イメージ
店舗外観イメージ